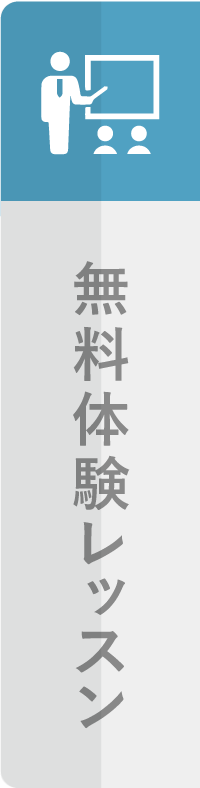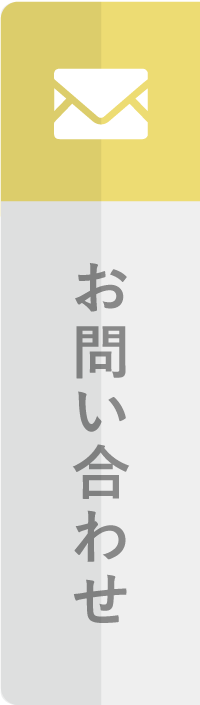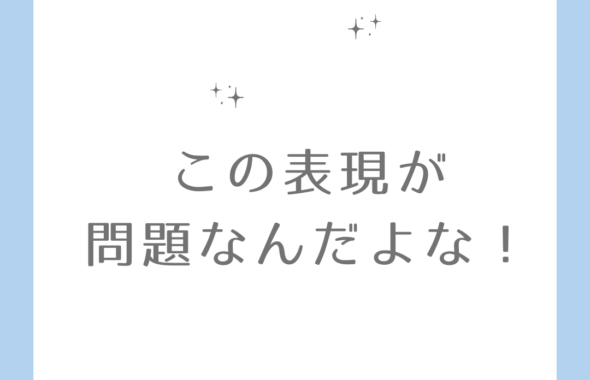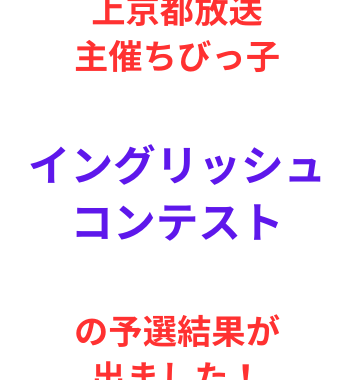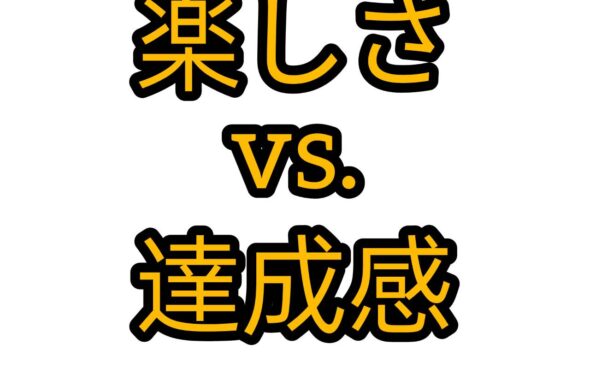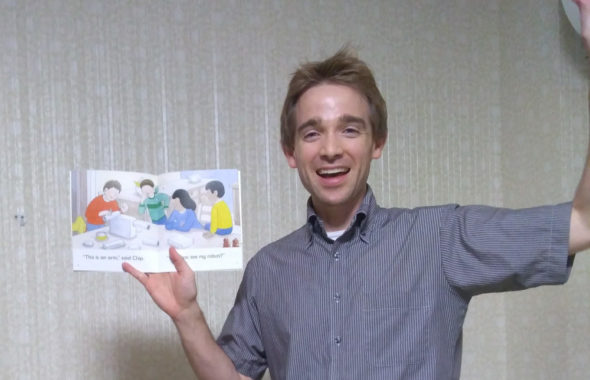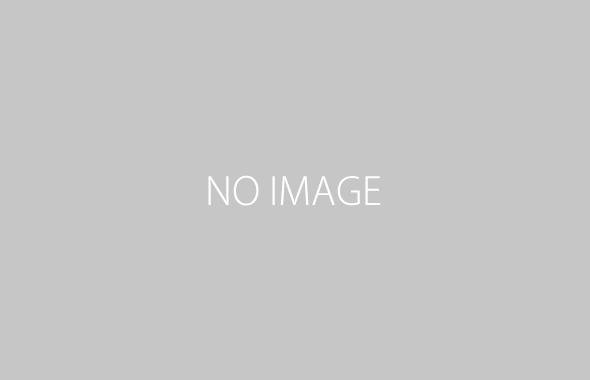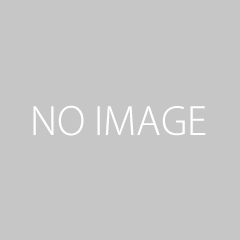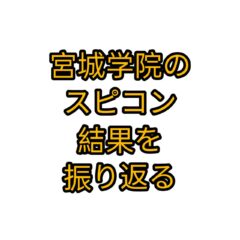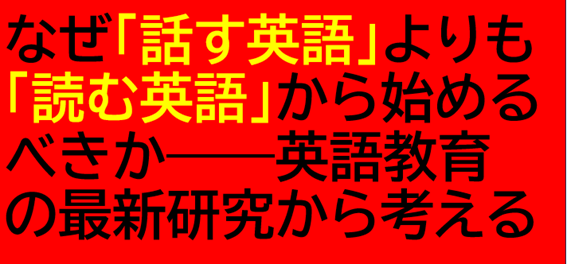
なぜ「話す英語」よりも「読む英語」から始めるべきか——英語教育の最新研究から考える
なぜ「話す英語」よりも「読む英語」から始めるべきか——英語教育の最新研究から考える
私たちの教室がなぜ「まず読むこと」を軸にした英語教育を行っているのか、第二言語習得理論(Second Language Acquisition, SLA)の観点からご説明します。
✅「話す練習」だけでは英語は定着しない
「英語を話せるようになってほしい」という保護者の思いはもっともです。
しかし、発話(output)だけを繰り返しても、言語能力の定着にはつながりません。
SLA研究の第一人者であるスティーブン・クラッシェン(Stephen Krashen, 1982)は、言語習得において最も重要なのは「理解可能なインプット(comprehensible input)」であると述べています。
この考え方に基づき、私たちの教室ではまず多読と多聴による大量のインプットを重視します。
✅ 多読と語彙習得の関係
Elley and Mangubhai(1983)の研究では、物語中心の多読プログラムが語彙力・文構造理解・読解力において大きな効果をもたらすことが明らかになっています。
また、Nation(2001)は、語彙習得には「文脈の中で自然に語を出会う頻度」が極めて重要であると指摘しています。
したがって、私たちは生徒一人ひとりのリーディング量を記録し、語数ベースでのインプット管理を行っています。
✅ フォニックスは読みの土台を築く
「読める子は話せるようになる」という背景には、音と文字の対応(phoneme-grapheme correspondence)の理解があります。
Juel (1988) の研究は、フォニックス指導によって音韻認識が高まり、読解力全体の向上につながることを示しています。
私たちの教室でも、幼児期から丁寧なフォニックス指導を行い、「読める音の体系」を確立することで、その後の読解・発話につなげています。
✅ 小学生からのアウトプット指導:即興ではなく蓄積から
発話練習は決して不要ではありません。
むしろ、一定量のインプットが蓄積された後に行うことで、正確で意味のあるアウトプットが可能になります。
Swain(1995)の「出力仮説(Output Hypothesis)」は、学習者が自らの言語使用を通じて気づきを得る重要性を指摘しています。
そのため、私たちは、自己紹介や簡単なスピーチ練習などを通じて、言語化する力の訓練も段階的に行います。
✅ 教室の特徴:教育学に基づいた運営
-
読解中心のインプットカリキュラム
-
3,000冊以上の英語絵本と記録管理システム
-
Phonics→Reading→Retelling→Speakingの段階的スキル設計
-
最大6名の少人数制クラスでの対話的指導
-
大学でも教鞭をとる講師による監修
📩 無料体験レッスンのご案内
もしこのアプローチにご興味をお持ちいただけたなら、まずは無料体験レッスンで実際の授業をご確認ください。
研究に裏付けられた教育方針を、現場でどう実践しているのかを体感していただける機会です。
ご希望の方は、ご連絡ください。
参考文献(一部)
-
Krashen, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition.
-
Elley, W. B., & Mangubhai, F. (1983). The impact of reading on second language learning. Reading Research Quarterly, 19(1), 53–67.
-
Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language.
-
Juel, C. (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children. Journal of Educational Psychology, 80(4), 437–447.
-
Swain, M. (1995). Three functions of output in second language learning. In Principle and Practice in Applied Linguistics.
ご質問やご相談もお気軽にどうぞ。
ご連絡、お待ちしております。