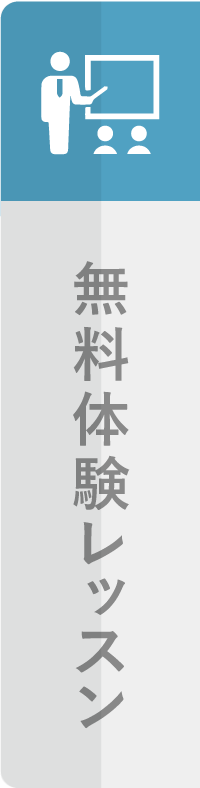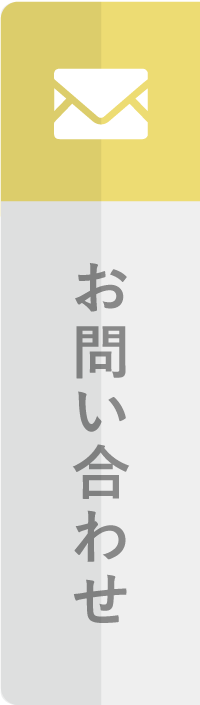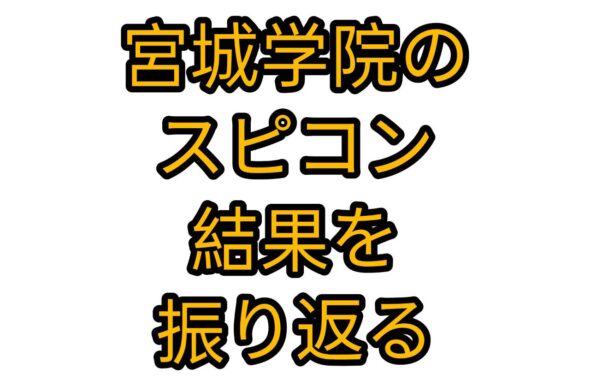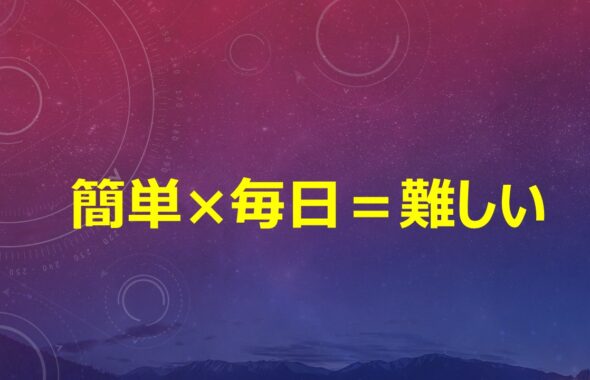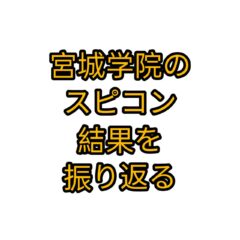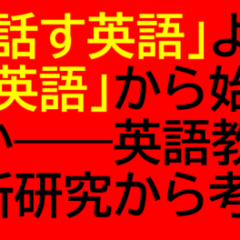挨拶=力
教室に集まるのは、アルゴリズムのロボットではなく、気持ちを持った人間です。
その時の気持ちの持ちように大きく左右される人間です。
ならば、気持ちを管理することによって、授業をもっと もっと よくしていくのが、1つの戦略です。
1~2カ月前から、生徒の教室の入室際の「挨拶」を重視してる。
入室と同時に「Hello!」といった「英語を身に付けるための挨拶」ではない。
日本語での挨拶です。
本人の母語であり、思考と気持ちの土台である日本語で、上をみて、はっきりと「こんにちは!」ということを徹底しはじめた。
言い忘れや、なーなーの形だったら、一回出て、もう一回入室する。
なぜ?
「それって、結構昭和じゃない?」
→挨拶を通して、その場の雰囲気をよくし、相互尊敬度を向上されるのが、『昭和的』なら、昭和歓迎です。
この方針を導入した理由を挙げれば、切りがない。
でも、以下の事柄が主な理由。
①
(入室時)
先生:「~~ちゃん、こんにちは!」
生徒:「…….」とそのまなま座る。
それか
(入室時)
生徒:「こんにちは!」
先生:「~~ちゃん、こんにちは!.」
どっちの方が先生の気持ちをよい方向に刺激する?
もちろん、後者でしょ?
たった一言の挨拶の言葉によって、先生の気持ち上がる。先生の本気度も上がる。
確かに、「どんな状態下でも、最高の授業のするのが先生でしょ?だから、生徒の挨拶の有無によって、影響されるのは、二流の先生。」との反論があるかもしれない。
でもさ、
甲子園、ウィンターカップ(高校バスケ)、超一流企業の多くで、挨拶が徹底している話をきくのはなぜ?
管理者や監督は、その場の「雰囲気」というのは、その場にいる人のパフォーマンスを向上することが分かっているから。
すべては繋がっている。
ましては、「コミュニケーション」を商品としている「語学教室」なら、一層、挨拶が定着していて、当たり前。
だから、英語教室で、挨拶慣れしていない子に挨拶慣れをさせるのは、生徒の配慮です。
先生がもっと もっと いい授業ができるようになり、それによってあなたももっと もっと伸びるように、、、、あなたが先生を手伝って、、、ということです。
②気持ちの切り替え
教室は楽しい所であってOK!
レッスンも楽しい時間であってOK!
ただし、レッスンと教室は、自由に行き来して、やりたいことができる公園や家のリビングではない。
公園や自分のリビングではやらないような言葉遣いを使うことによって、気持ちもモード切替が始まる。
「はい!気持ちを切り替えよう!!!って直接伝えたって、子供には響かないでしょう。
私が中学校・高校で、「はい。授業が始まります。気持ちを切り替えて」とか、散々「直接」、聞かされたけど、気持ちの変化への影響は皆無だった。
ただ、中学校の職員室にはいるときは、「失礼します。」と言って入った。自然と、気持ちが変わる。
公園や下校時は、周囲に友人だけがいた。しかし、今から、友人もいるが、「先生」もいる、という意識を持った方が絶対x100、レッスンの効果が高い。
そして、グループレッスンである以上、集団で雰囲気を作っていく。
これまで、挨拶を「本人の意思」に任せていた所があった。でも、挨拶率100%を達成できていないのは、子供のせいではない。
「こんにちは」と、挨拶をしなくてもいい環境を作りだしていた、私に原因があった。まさに、責任転嫁と脚下照顧です。
大きな扉も小さな蝶番で開く。
====
今、晩翠通りドトールの外で書いている。景色は、きれい。
そと天気や景色に左右されず、
室内を気持ちのいい場所にできるのが、素直で気持ちのこもった5文字。
~~「こんにちは」~~